「USJを劇的に変えた、たった1つの考え方」森岡毅
副題:成功を引き寄せるマーケティング入門
📕はじめに パワポに自信が持てなかった僕
社会人3年目、業職の僕は「プレゼンが苦手」という自覚があった。
話す内容は上司にチェックされるし、資料もパワポのテンプレートを使えば何とか形にはなる。
でも、いざ発表の場になると、相手の反応がいまひとつ。頷きも少なく、質問も出ない。
終わった後に気まずい空気が流れることもあった。
自分では頑張って作ったつもりなのに、なぜ伝わらないのか。
上司に相談しても「もう少し工夫して」と言われるだけで、改善の糸口は見えなかった。
そんなある日、書店でふと目に入ったのが、『USJを劇的に変えた、たった1つの考え方』という本だった。
著者は、USJをV字回復に導いたマーケター・森岡毅さん。
ビジネス書とは思えないポップな表紙に惹かれて手に取ったのが、僕のプレゼン人生を変える最初の一歩だった。
📘見どころ①“お客さんの気持ち”を軸にした資料作り
この本には、USJが再建する中で森岡さんが実践した「マーケティングの本質」が、わかりやすい言葉で書かれている。
なかでも心に刺さったのが、「自分目線ではなく“お客さん目線”で考える」ことの重要性だった。
それまでの僕は、「会社が伝えたいこと」をパワポに詰め込んでいた。
製品のスペック、売上見込み、競合比較。
とにかく事実と数字を並べて、「どうだ!」と主張するスタイルだった。
でもそれでは、聞いている側にとって“自分ごと”にならない。
USJも、かつては「テーマパークが伝えたいこと」を押し出しすぎて失敗していたという。
森岡さんはそれを、「ゲストの気持ちに徹底的に寄り添う」ことでV字回復させた。
その発想をプレゼンに応用できないだろうか?
そう思った僕は、次の社内発表の資料づくりから、軸を“聞き手の気持ち”に変えてみることにした。
なぜ“数字の羅列”では伝わらないのか?
プレゼンではつい、数字をたくさん入れたくなる。
努力の証拠にもなるし、説得力があるように感じるからだ。
でも本を読んで気づいたのは、「数字だけでは人は動かない」ということだった。
たとえば「前年対比120%の売上増加」と言われても、それがなぜすごいのか、どんな意味があるのかが分からなければ、相手の心には響かない。
森岡さんは、マーケティングでも「数字ではなく、人間の感情や行動にフォーカスする」ことを徹底していた。
USJでハリーポッターのアトラクションを導入する際も、データだけでなく“魔法の世界に没入したい”というゲストの心理を分析して戦略を練っていたという。
僕も資料作りの中で、単にデータを並べるのではなく、「この数字が相手にとってどんな意味を持つか?」を意識するようにした。
それだけで、スライドの構成や言葉の選び方ががらりと変わった。
📗見どころ②共感→課題→解決のストーリー構成
特に参考になったのが、「プレゼンも物語のように組み立てる」という考え方だった。
感情を動かすには、いきなり解決策を提示するのではなく、まず“共感”から始める。
「あなたと同じように、私もこんなことで困っていました」
そこから“課題の明確化”に進み、最後に“解決策”を提示する。
これは、まさに映画やドラマの脚本のような構成だ。
プレゼンの構成を以下のように意識するようにした:
① 共感:「この業界のこんな課題、感じたことありませんか?」
② 課題:「実は、こんな背景がありました」
③ 解決:「そこで私たちが考えたのが、こちらの提案です」
すると、聞き手の表情が変わるのを感じた。
「自分のことを考えてくれている」と思ってもらえるのだろう。
それまでの“資料を説明するだけのプレゼンから“相手にストーリーを届ける時間”に変わっていった。
数週間後、営業部のチームミーティングで、僕は新しいプロジェクトの提案プレゼンを任された。
テーマは、既存顧客へのアップセル施策だ。
これまでは「過去の売上データを分析し、類似案件の提案」くらいで終わっていたが、今回は森岡式の“お客さん目線”を徹底的に取り入れてみた。
スライドの1枚目には、数字ではなく、顧客の声を載せた。
「最近、新しい提案がなくて物足りない」といったリアルな感想だ。
そこから「私たちはお客様の変化に追いつけていないのでは?」という課題を提示し、最後に具体的なアップセル施策の提案へとつなげた。
プレゼンが終わると、上司がポツリとこう言った。
「今回、すごく“聞き手の気持ち”を意識してるね。わかりやすかった」
その一言が、これまでプレゼンに悩んでいた僕にとって、どれほど大きな意味を持ったかは言葉では言い尽くせない。
📙まとめ:考え方を1つ変えるだけで、伝わり方が変わる
『USJを劇的に変えた、たった1つの考え方』は、ビジネス書でありながら、プレゼンやコミュニケーションにも直結する“人の心の動かし方”を教えてくれる本だ。
僕はこの本を読んで、「プレゼンは、伝えたいことを伝える場ではなく、相手に届く形で届ける工夫をする場なんだ」と気づいた。
資料の内容、話し方、構成。
それらすべては“誰に届けたいか”を中心に組み立てるべきだ。
今では、プレゼンのたびにこの本の一節を思い出している。
「正しいことを言うよりも、伝わるように言うほうが大事」
もしあなたが、「伝えること」に悩んでいるなら、ぜひ一度この本を手に取ってみてほしい。
きっと、あなたの中の“伝え方の軸”が静かに変わっていくはずだ。

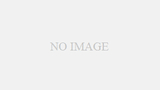
コメント