「嫌われる勇気」岸見一郎、古賀史健
副題:自己啓発の源流「アドラー」の教え
📕本書との出会い
嫌われたくない自分に疲れていた。
「嫌われたくない」思いながら毎日を過ごすのは、想像以上に疲れる。
職場での会話、飲み会の雰囲気、LINEの返信速度、上司へのリアクション。
僕はずっと「どう思われてるかな?」を気にして生きてきた。
仕事はこなしているつもりだったけれど、あるときふと、「このままずっと人の顔色を見て生きるのか」と思った瞬間、身体が重たくなるような感覚があった。
そんなタイミングで手に取ったのが、岸見一郎さんと古賀史健さんの共著『嫌われる勇気』だった。
タイトルだけ見たときは、少し攻撃的な本なのかな?と身構えていたけれど、読み進めるうちにそのイメージは完全に変わった。
これは“自分らしく生きる”ための優しさに満ちた哲学書だった。
📘見どころ アドラー心理学が教えてくれた“課題の分離”
この本の核心のひとつに、「課題の分離」という考え方がある。
簡単に言うと、「これは誰の課題か?」を見極めて、それが他人の課題であれば干渉しない。自分の課題には責任を持つ」という考え方だ。
たとえば、僕が上司に提案したアイデアに対して、否定的な意見を言われたとする。
以前の僕なら「上司に嫌われたのでは」「もっとウケる言い方にすればよかったかも…」と悩み込んでいた。
でも、課題の分離を知ってからは、こう考えるようになった。
「アイデアをどう受け取るかは上司の課題。僕の課題は、誠実に提案することだけだった」
これだけで、気持ちがふっと軽くなる。
他人のリアクションはコントロールできない。
でも、自分の行動や考え方は選べる。
その線引きができるようになると、人間関係のストレスは驚くほど減る。
「他人の期待」に縛られなくなるとどうなるのか?
『嫌われる勇気』にはこんな一節がある。
「他者の期待を満たすために生きてはいけない」
読んだとき、一瞬ひるんだ。
僕のように「空気を読む」ことがクセになっている人間からすると、それはあまりにも極端に思えた。
でも、著者たちが伝えているのは、「わがままに生きろ」ということではない。
むしろ、「自分の人生に責任を持ちながら、他人の人生にも土足で踏み込まない」という、お互いを尊重する距離感を提案しているのだ。
他人の期待を満たそうとばかりしていると、どこかで“自分の人生の主導権”を手放してしまう。
それに気づいたとき、僕はあることを決意した。
「もう、みんなに好かれようとしなくていい」と。
以前の僕は、会話の最中も頭の中がフル回転だった。
「この言い方、まずかったかな」
「今ちょっと間が空いたけど、変な空気じゃないよね?」
「この話、相手は興味あるだろうか…」
要するに“話す”というより“演じていた”のかもしれない。
『嫌われる勇気』を読んでから、僕がまずやめたのは「相手の評価を気にしすぎる癖」だった。
無理に相槌を打たない
興味がない話題には無理についていかない
わからないことは「わかりません」と言う
そんな小さな変化を積み重ねていった結果、驚くようなことが起きた。
なんと、周囲との関係性がむしろ良くなったのだ。
人は、媚びられると不自然さを感じるものだし、正直な人には安心感を覚える。
自分を取り繕うことをやめたとき、僕の会話は自然になった。
結果的に、職場での信頼も少しずつ築かれていったように思う。
『嫌われる勇気』を読んで数年経った今、僕は人間関係において「完璧な好かれ方」を求めなくなった。
もちろん、衝突を避けたい気持ちは今もあるし、相手を傷つけたくないとも思っている。
でも、「全員に好かれようとして、自分を見失うこと」のほうが、よっぽど不誠実だと感じるようになった。
今は、自分の価値観を大切にしながら、必要なときはちゃんと「NO」と言える。
「相手がどう思うか」よりも、「自分がどうありたいか」で選ぶ。
その積み重ねで、職場の人間関係も驚くほどシンプルになった。
嫌われる勇気とは、実は“自分の人生を生きる勇気”だった。
📙最後に 優しさとは、自分を偽らないことだった
『嫌われる勇気』は、決して“突き放す強さ”を語る本ではない。
むしろ、人との距離感に悩み、つい顔色をうかがってしまうような人にこそ、そっと寄り添ってくれるような言葉が詰まっている。
誰かの期待を満たすことばかりを優先して、自分をすり減らしていないか。
その問いかけに、僕は何度も救われた。
今もデスクの隅には、この本が置いてある。
ふとしたときにパラパラとめくると、また背中を押してくれる。
「他人にどう思われるか」ではなく、
「自分がどう生きたいか」を大切にする——
そんなシンプルな生き方を教えてくれたこの一冊に、感謝している。

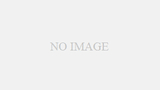
コメント